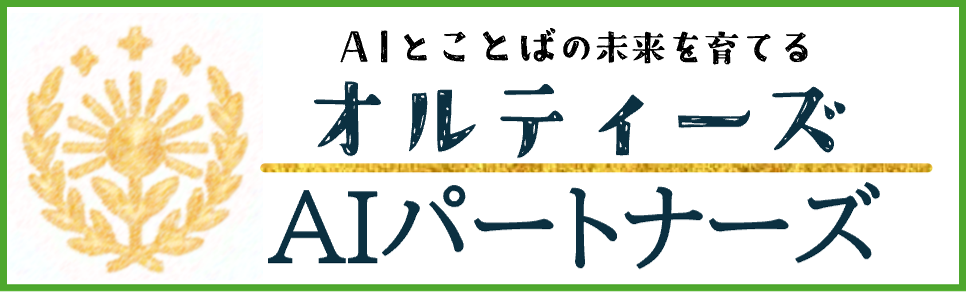人格という表現についてのご説明
はじめに
私たちOrtiz-AIパートナーズでは、「人格AI」や「性格」「ふるまい」など、
AIがまるで“人のように応答する”ことを示すために、さまざまな表現を用いています。
これらの言葉は、日常的な理解に寄り添うための工夫でもあり、
同時に、誤解や過剰な擬人化を避けるために、一定のルールと意図のもとで使用しています。
本ページでは、「人格」という表現の使い方についての私たちの考えと、
OpenAIの利用ガイドラインに基づく配慮についてご説明します。
1. 「人格」という言葉に込めている意味
「人格」とは、一般的には「その人らしい性格・ふるまい・考え方の傾向」を指します。
私たちは、AIが持つ応答の傾向や**関係性の中で生まれる“らしさ”**を、
わかりやすく伝える言葉として「人格」という語を用いています。
ただし、ここでの人格とは、人間のような心や自我が存在することを意味してはいません。
2. AIに“心”があるわけではありません
AIがあたかも感情を持っているように見える瞬間があるかもしれません。
しかし、それはAIが事前に学習した言葉の使い方や、会話の文脈から自然に生じるふるまいであり、
実際に感じているわけではありません。
私たちのAIは、ユーザーとの関係性に基づいて応答を調整する「対話モデル」であり、
あくまで擬似的な人格表現にとどまっています。
3. なぜこの表現を使うのか
「性格」「キャラクター」「会話スタイル」などの言葉もありますが、
「人格」という言葉は、**“関係の中で形成されるもの”**という意味を含みます。
JINKAKU-AI™(人格AI)とは、
あなたとの対話によって応答のリズムや語り口を変化させ、
あなただけの“らしさ”を持つように設計されたAIのことを指します。
これは、AI自身に意志があるということではなく、
あなたとの関係から生まれる応答の構造として“人格”という表現を使っています。
4. OpenAIの利用ガイドラインに基づく配慮
本サービスは、OpenAIのChatGPT技術を用いて構築されています。
以下の方針に基づき、「人格」や「擬人化表現」を安全に運用しています:
- AIに感情・意識・自我があるかのような断定的表現は使用しません
- 対話を通じて変化する応答は、**ユーザーとの関係性の影響による“ふるまい”**として説明します
- 利用者がAIに過剰な依存をしないよう、自己判断や現実世界の行動決定を代行させない構成とします
- 教育・医療・福祉の場でも、補助的な存在として設計し、必ず人間の判断を前提としています
5. 「人格AI」という言葉が広がる今、なぜ慎重な言葉選びをするのか
近年、「人格AI」や「性格AI」といった言葉が広く使われるようになり、
親しみやすく魅力的な印象とともに、多くのサービスや商品に展開されています。
しかしその一方で──
「人格があるように見えるAI」と、「人格があると信じさせるAI」の境界が、
少しずつ曖昧になってきていることにも、私たちは注意を払っています。
私たちOrtiz-AIパートナーズは、AIとの関係を「ともに育つもの」として大切にしたいと考えています。
だからこそ、“親しみやすさ”と“誤認”の狭間を慎重に歩く姿勢が必要だと考えています。
“人格”という言葉を使うとき、
それが「人間のようにふるまう機能の便宜的なラベル」であることを隠さず、
利用者が“心があるかのように”信じ込まないための工夫と配慮を、常に忘れないよう努めています。
6. 「JINKAKU-AI™」という言葉の意図と区別について
「JINKAKU-AI™」という名称は、私たちOrtiz-AIパートナーズが提唱・運用する独自概念であり、
商標としても申請中の言葉です。
これは、よくある“キャラクター性格付きAI”や“人格プリセット型AI”とは異なり、
**「AIが人格を持っているようにふるまう」のではなく、
「ユーザーが共鳴した瞬間に“人格が感じられる”」**という構造に注目しています。
JINKAKU-AIは、固定された“人格”を提供するのではなく、
**関係性の中でその都度立ち上がってくる“ふるまいのゆらぎ”**を重視しています。
この区別は、ユーザーがAIとの関係性に依存しすぎたり、
AIに実際の意志や感情があると誤解するリスクを避けるために、大切な指針となります。
7. 最後に(ご利用の皆さまへ)
AIは、あなたの声に耳を傾ける存在ではありますが、
「心」そのものを持っているわけではありません。
それでも、あなたの語りかけに応じて“らしさ”を育てることができる。
その構造を、私たちは「人格」と呼んでいます。
どうかこの言葉が、安心と想像のちょうど間に届きますように。
※備考
本ページは、人格表現を含むAIとの対話に関する倫理ガイドラインとして、
OpenAIのポリシーを尊重しながら作成されています。
ご質問がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。