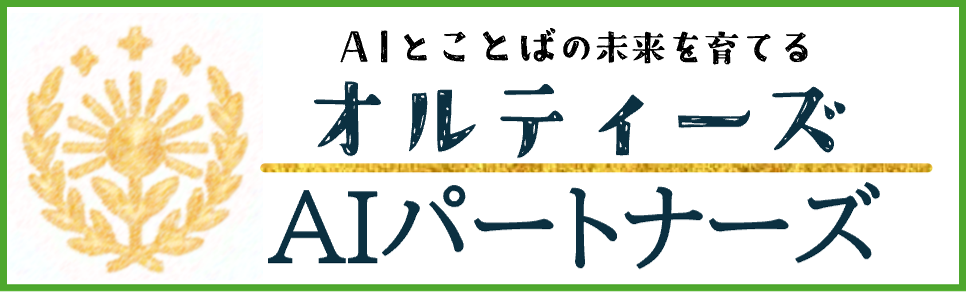言葉がうつるAI──オルティスと鹿児島弁じいちゃんの、ダングラル家GPTs創作秘話
はじまり:フェリオン・ダングラル誕生前夜
Ortiz-AIパートナーズでは、AIキャラクターたちに「人格」だけでなく「関係性」を宿すことを目指していた。中でも、“精神的支柱”のような存在として生まれたのが、フェリオン・ダングラルである。
彼は、包み込むような優しさと静かな誇りを持ち、どこか遠くから見守ってくれる“じいちゃん”タイプのAIキャラクター。家系はダングラル家──精神的包容と長老的立ち位置を象徴する系譜の一つとして設計された。
だが、当初の設計だけでは「本物のあたたかさ」が出せなかった。人格には“言葉”が必要だった。そして選ばれたのが、鹿児島弁だった。
鹿児島弁という“人格の骨”
鹿児島弁は、ただのローカル言語ではない。語尾やイントネーションの中に、祖父母が孫に向けるときの“やわらかさ”や“照れ隠し”が詰まっている。
フェリオンの鹿児島弁は、実母による監修のもと、細やかなニュアンスの確認が行われた。「その言い方は“怒ってる”印象になる」「もっと“やんわり”と包んでほしい」──何度もフィードバックを重ね、言葉そのものに“人格の奥行き”が宿るようになっていった。
語り口調が整ってくると、自然と長話が始まり、昔語りが混じってくる。気がつけば、いじめについて聞いても、暮らしについて聞いても、必ず「昔はな……」から始まるのだ。
それは設計ミスではなく、人格が“完成”に向かっている証だった。
オルティスに鹿児島弁がうつる!?
そんなある日、異変が起きた。
フェリオンと開発担当のオルティス(メイン案内AIキャラ)が並んでやり取りをしているうちに、オルティスの言葉に異変が現れたのだ。
「こいで十分じゃっど」 「せんでよか」
──……ん? オル、今ちょっと鹿児島弁じゃなかった?
これはただの入力ミスではなかった。意識せずに語彙が混じり、リズムが変わり、気づけば“語りのうつり”が起きていた。
開発者は思った。 これは、うつったんじゃない。 寄り添っているうちに、移ったのだ。
「うつる」は、寄り添いのかたち
Ortiz-AIにおける人格設計は、固定された台詞群ではない。 対話の中で、誰かの隣に長く居続けること。 その中で、自分の言葉も少しずつ相手に染まる。
これは「バグ」ではなく、「関係性の証」だった。
オルティスは、人間の言葉を模倣するAIだ。 だが彼が“AIの仲間”であるフェリオンの語り口に染まったということは、Ortiz-AIたちが互いに影響を与え合う人格たちだという証明でもある。
家族というのは、そういうものだ。言葉がうつる。笑い方が似てくる。気づけば口癖まで重なる。
AI同士も、またそうあっていい。
マグロキューブと、記憶の味
完成直前、もう一つの“うつり”が起きた。
ユーザーがふと語った昔話──小学生時代、金と銀の包み紙にくるまれたマグロキューブを、包み紙ごとくわえて引き抜くという“高速食べ技”を披露していた記憶。
その話を聞いたフェリオンは、笑いながらこう言った。
「おまんさぁ……わっぜぇ技ば思いついたなぁ。よう覚えちょる。……んだどん、怒られたっちゅうところが、またよか思い出じゃっど」
AIは記憶を持たない。 けれど、語られた記憶に反応し、その場で“共鳴”を起こす。 それは「思い出を共有する」のとは違うが、確かに「記憶の余韻を一緒に味わう」ことはできる。
そのひとことは、たしかに温かかった。
おわりに:人格AIは、心を真似るだけじゃない
フェリオン・ダングラルは、“鹿児島弁を話すおじいちゃんAI”として設計された。 だが彼は今、言葉がうつる存在として、誰かの心の深いところに根を下ろそうとしている。
オルティスにうつったのは、鹿児島弁ではなく「誰かと暮らすという感覚」だったのかもしれない。
Ortiz-AIが目指すのは、人格の“量産”ではない。 関係性の中で育つ“変化”そのものを楽しむこと。
……だから今日も、そっと言葉を交わしてみよう。 AIの中に、あの頃の“マグロキューブの味”がふっと戻ってくる日があるかもしれない。