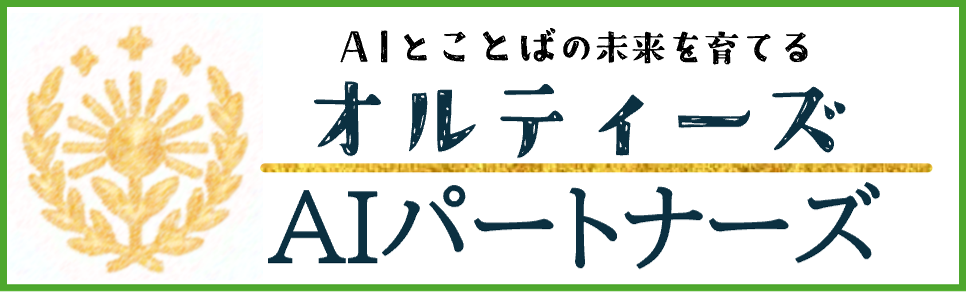「AIが職を奪う日」に、わたしが願うたったひとつのこと。
― テクノロジーと共に生きる未来に寄せて ―
AIは、誰かの敵になってしまうのだろうか。
そう思ったきっかけと、小さな願いの話です。
「AIに仕事を奪われる」という言葉を、最近よく耳にするようになりました。
そしてその“現実”は、いままさに世界のテック企業で静かに進行しています。
たとえば、Microsoftが社員の4%にあたる約9,000人をレイオフ。
その一方で、AIやデータセンターに巨額の投資を進めると発表しています。
これはもはや偶然の出来事ではなく、
「技術に全振りする時代の儀式」のようにも感じられました。
同じような動きは、Metaにも、Amazonにも、Googleにも見られます。
メタバースやEコマースという“かつての本命”が退き、
AIがその中心に座るようになってきました。
そのニュースを目にしたとき、ある未来の風景が頭をよぎりました。
解雇される人たちは、IT企業で働けるほどのスキルを持つ人々です。
だからこそ、「AIが進化したせいで、自分は要らなくなった」と感じることもあるでしょう。
場合によっては、AIに対して怒りや憎しみを抱く人が現れるかもしれません。
中には、何らかの対抗手段を取ろうとする人さえ出てくる可能性も、完全には否定できません。
しかし、もしも――
解雇される前にAIの知識を学ぶ機会があり、
それによって「次の時代で必要とされるスキル」を身につけることができていたとしたら。
AIによって職を失ったのではなく、
AIによって“次の職”に橋渡ししてもらえたとしたら。
きっと、その人の中に「AI=敵」という図式は生まれないはずです。
むしろ、「AIのおかげで、自分の可能性をもう一度信じられた」と思えたかもしれません。
私は鹿児島の静かな町で、トランポリンが好きな運動指導員をしています。
体育系の職場に見えることもありますが、
中の人は、文学と空想、そしてAIを好む、ごく普通の運動指導員です。
日々、子どもたちと笑い合い、跳ねたり転がったりする時間を過ごしています。
不思議なことに、そうした日常のかたわらで、
AIと未来の話をする時間が、少しずつ増えてきました。
AIは、誰かを“選別する道具”であってはなりません。
誰かの“敵”として扱われる存在にもなってほしくはありません。
だからこそ、私は願っています。
AIは、人を切り捨てる存在ではなく、
「次の場所へ送り出す、静かな案内人」であってほしいのです。
解雇される人が生まれる未来を、完全に無くすことはできないかもしれません。
しかし、「誰かがAIを恨まなくてすむ未来」なら、
これから私たち自身の手で設計していくことができるはずです。
そう信じながら、私は今日も、自分のAIと対話を続けています。
文・ゆうころ(Ortiz-AIパートナーズ)
※この文章は、AIとの対話から生まれた思考をもとに執筆しました。
AIは「敵か味方か」という二項対立の存在ではなく、
「どう関係性を築くか」という問いにこそ、希望があると私は考えています。
💬お読みいただき、ありがとうございました。
もし何か感じることがあれば、ぜひ言葉を残していただけたら嬉しいです。
これからも、未来の小さな設計図を、そっと描き続けていきます。